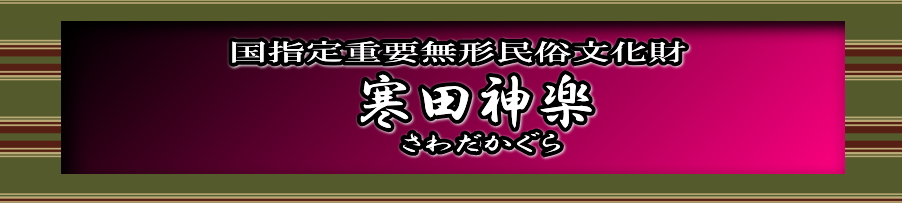 |
|
|
 |
<無形民俗文化財公開情報>
<名 称>寒田神楽(さわだかぐら)
<種 別>国指定重要無形民俗文化財
<公 開 日>毎年1月1日、毎年5月4日~5日、毎年10月第3日曜
<公開場所>老人いこいの家「やまさと」(福岡県築上郡築上町寒田)
<時 間>1月1日は14:00~ 5月4日は20:00~ 5月5日は13:00~ 10月第3日曜は15:00~
<駐 車 場>老人いこいの家「やまさと」の駐車場は神楽の舞場になるため使用不能
公道や空き地に駐車可能
<ト イ レ>老人いこいの家「やまさと」にある
<問合せ先>築上町教育委員会 Tel.0930-52-0001
(注意)公開場所や日時は変更になる場合があります |
 |
 |
<NIA取材記>
取材は2018年5月5日に行った。
場所がわからずだいぶん迷った。山霊神社は小山の山頂部分にあって参道は細く、
普通車は無理と思われたので参拝しなかった。
山霊神社の1の鳥居のすぐ横が「老人いこいの家「やまさと」」である。
神楽はここの駐車場で奉納される。
5月の神楽は式神楽だけで、湯立は10月に行われるそうである。
神奈川県の宮城野の湯立神楽は取材したが、こことはだいぶん違うようなので、
10月に取材に行こうと思っている。
この度の神楽には小学生の参加があった。
まだまだの感はあったが後継者の問題はなさそうだ。
老人いこいの家「やまさと」(0930-54-0478)にナビをかければ迷わず行けますよ。
2018年5月29日 池松卓成 記す |
<寒田神楽の内容説明>
寒田神楽の由来は定かでないが、寛文5年(1665)、地元山霊神社の火災の際に神職の岡田平治が火災を鎮めるために、
鎮火祭文を唱えて神楽を舞ったという。2年間かけて山霊神社は再建され寛文7年9月に神迎神楽を奉納し遷宮を行った。
それ以来、山霊神社奉楽士として、秋祭の鎮火祭で湯立神楽が奉納されるようになったと伝えられている。
京築地区の神楽は、明治以前は神職以外では舞うことは許されない社家神楽(神職神楽)であった。
明治の神職世襲制度の廃止に伴い、社家神楽が禁止されたため、明治中期に旧築城郡伝法寺村岩戸見神社の宮司熊谷房重が
氏子に直伝し、それ以来一度も絶えることなく奉納されている。
舞方、囃子方共に、「山霊神社奉楽定」に基づき世襲制により受け継がれ、家筋について強く意識されていたが、
昭和43年に氏子であれば誰でも舞えるように改められ、同時に宮柱、宮司を中心に神楽講も発足した。
現在では、住民だけでなく寒田地区出身者であれば参加できるようになった。
寒田神楽の大部分は出雲神楽の系統に属する神楽である。
式神楽に加え、湯立神楽が有名である。平成26年には、十年ぶりに湯立神楽が奉納された。
湯立神楽は修験道の影響を受けた神楽である。33把の薪木を燃やして鉄釜で湯をたぎらせ、猿田彦神が探湯(くがたち)をし、
その湯を振って祓い清め、祝詞奏上で火を鎮め、3名が火床の上を渡る。
舞庭に上部を幣で飾った約10mの孟宗竹(湯鉾)をよじ登り、「湯鉾」の上に取り付けた御幣を切り落とし、
逆様になって滑り下る。これを「幣切り」といい、御神霊の天孫降臨を意味するという。
平成28年に「豊前神楽」の1として国の重要無形民俗文化財に指定された。
寛文4年(1664)の手力雄命、元禄10年(1697)の天鈿目女命の神楽面が保管されている。
ところで、寒田地区は築城町内の他の地区と異なり、1地区1神楽1小学校となっているため、
築城町役場の尽力により寒田小学校全校児童全員に対して神楽が授業の一貫として教えられている。
子供神楽としての奉納は現在行われていないが、学校内の行事(文化祭、卒業式など)で舞っている。
将来は子供神楽の奉納も考えられている。本神楽は男性のみで舞うが、子供神楽は男女共舞う事が可能で現在10名程度が参加している。
|
   |
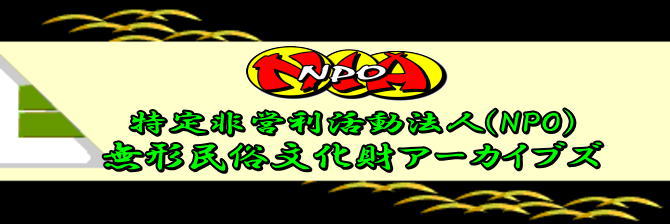 |
  |