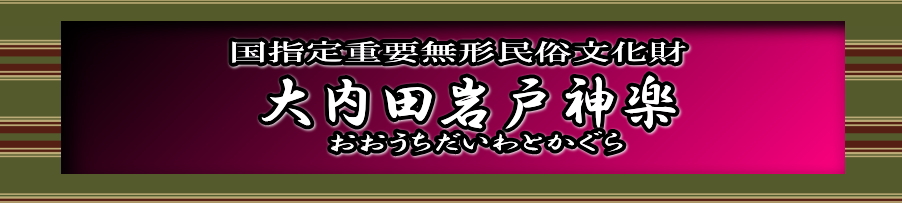 |
|
|
 |
<無形民俗文化財公開情報>
<名称>大内田神楽(おおうちだかぐら)
<種別>国指定重要無形民俗文化財
<公開日>毎年4月第4土曜日
<公開場所>大内田研修センター(福岡県田川郡赤村大字内田3535)
<時間>20:00~23:00
<駐車場>大内田研修センター前に15台程度駐車可能
<トイレ>大内田研修センターにある
<問合せ先>赤村役場政策推進室 TEL0947-62-3000
(注意)公開日時は変更になる場合があります |
 |
 |
<NIA取材記>
取材は2018年4月28日に行った。大内田研修センターがわからず、
赤村役場で聞けば分かるだろうと役場に行った。
土曜日なので職員はいなかったが、駐車場におられた人に場所を聞いた。
田川地区水道企業団の看板から左折したらよいとの事。
役場から3kmはあるだろう。やっとのことで大内田研修センターに着いた。
午後3時頃だった。神楽は午後8時からだそうでだいぶん時間がある。
午後6時ごろ弁当を食べて撮影準備にかかった。
午後7時30分。だいぶん観客が増えてきた。午後8時、太鼓が鳴り出し神楽が始まった。
小学校高学年の男児による「撒米」が舞われた。とても上手で、拍手が沸き起こった。
「御神先」では鬼と式部の争いは見どころがある。
鬼は急に観客席に行き、母親の手から幼児を奪い取る。
泣き叫ぶ幼児、何でもない様子の幼児、いろいろな個性が見られ面白い。
午後11時頃、熱気の中、神楽は終わった。
池松卓成 記す
|
<大内田岩戸神楽の内容説明>
大内田地区の郷社として大祖神社がある。
古くは、戸城山の山頂にあったそうであるが、ここに城を築くことになり延元3年(1337)に麓に社は移された。
それ以来、数百年地区の氏神として崇拝されている。この神社に奉納されているのが大内田神楽である。
大内田の岩戸神楽は、明暦元年(1655)に始まるという。
当時、この村に農耕用の牛馬に疫病がはやり、人々にも及んだので、村人一同が大祖神社に願をかけたところたちまち治まったという。
このありがたい徳を尊び、そのお礼の行事を決めるべく神籤を引いたところ、「四月神楽をせよ」の神意が出た。
これが大内田神楽のはじめという。
幾度かの存続の危機もあったが、「家が三軒になるまでは神楽を続ける」という万年願として神楽がなされている。
明治年間まで、築上群築城町「赤幡神楽(国指定重要無形民俗文化財)」を主として呼んでいたという。
現在の神楽は、赤幡神社の神職、神太郎右衛門を招いて赤幡神楽の指導を受け、12人の神楽講で始まった。
それ以来、大内田神楽として舞われてきたが、その所作の基本型は拝礼、うち込み(左右三べん)、舞切、かけ出し、折柳、
うち込み(左右三べん)、舞切、拝礼である。足はすって舞え。所作は上は大きく下は小さく、逆三角形のように舞えと教えられているという。
神楽の音楽は太鼓・笛・鉦でそれぞれ一人が行う。神楽の曲目は以下の通りである。
①撒米(まきごめ)
米をのせた三方を正面に置き、赤の狩衣の人が一人で舞う。拝礼後、左手で右袖先をつまんで回り、袖を翻して舞う。
その後、三方の米を右手にとり、左手で押さえて下がり
舞台をめぐって南(神輿に向かって右)に米をまく。それを西、北、正面に繰り返す。5分程度の舞である。
②折居(おりい)
赤と青の狩衣の二人ずつ、四人で舞う。左手に扇、右手に小幣をもって出る。
口上を唱えながら舞ったり、前後交代で舞ったり、輪になったりして舞う。
15分程度の舞である。
③御福(みふく) ④花神楽(はなかぐら)
⑤地割り(じわり)
この演技は暦に関するもので、春が木の神、夏が火の神、秋が金の神、冬が水の神である。
それぞれ90日間(旧暦・太陰太陽暦では1年は360日)を支配する。
ところが土の神には支配する季節はない。そこで、入る時期を要求し他の神々と斬りあうのである。
式部が仲裁し、春夏秋冬が始まる前の18日間(土用)、合計72日間を土の神に与えた。
これですべての神は72日間を支配することになった訳である。土の神は中央を支配し四季の主となった。
⑥幣切り ⑦前御神先 ⑧舞上御神先 ⑨綱御神先前段 ⑩綱御神先後段 ⑪盆神楽 ⑫岩戸の舞 などが公開される。
|
   |
 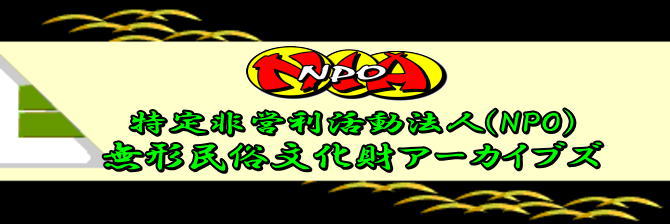 |
 |